雑節(ざっせつ)
季節の節目を示すもので、
二十四節気を補う意味合いをもつ
主に農作業と照らし合わせた季節の目安で、
日本の気候風土に合わせた日本固有の暦
雑節一覧
| 節分 | 春:2月3日頃 |
| 彼岸 | 春:3月21日頃前後、秋:9月23日頃前後 |
| 社日 | 春:3月中旬頃、秋:9月下旬頃 |
| 八十八夜 | 5月2日頃 |
| 入梅 | 6月11日頃 |
| 半夏生 | 7月2日頃 |
| 土用 | 夏:7月20日頃~8月6日頃 |
| 二百十日 | 9月1日頃 |
| 二百二十日 | 9月11日頃 |
節分(せつぶん)詳細
立春、立夏、立秋、立冬、
それぞれの前日を指す名称
現在は主に立春前日のみの事を指す
➝2月3日頃
彼岸(ひがん)詳細
春分・秋分を中日とし、前後3日を含む7日間
(春と秋で計14日間)
自然界すべてに感謝する「日願」の行事と
仏教由来の「彼岸」の行事が結びついたもの
など、諸説ある
【春の彼岸】
「3月21日頃(春分)」の前後7日間
【秋の彼岸】
「9月23日頃(秋分)」の前後7日間
社日(しゃにち)
春分・秋分に最も近い戊(つちのえ)の日
土地の神様に感謝する日
【春の社日(春社)】
種まきの時期(五穀豊穣祈願)
➝3月中旬頃
【秋の社日(秋社)】
収穫の時期(収穫を感謝する)
➝9月下旬頃
八十八夜(はちじゅうはちや)詳細
夏支度や農作業を始める目安
立春を第1日目として88日目の日
➝5月2日頃
入梅(にゅうばい)
暦の上の梅雨入りの時期
実際のその年の梅雨入りとは異なり、
梅雨に入る時期の目安として用いられてきた
太陽横径が80ºの時
➝6月11日頃
半夏生(はんげしょう)
梅雨の最盛期
(農作業を終える等の目安となる日)
太陽横径100ºの時
(かつては夏至から数えて11日目)
➝7月2日頃
土用(どよう)詳細
立春、立夏、立秋、立冬の各前日18日間ずつ
(「夏の土用」が取りざたされることが多い)
【夏の土用】
太陽横径117ºの時~立秋前日まで(約18日間)
➝7月20日頃~8月6日頃
二百十日(にひゃくとおか)
台風が襲来する日として注意をする
立春を第1日目として210日目
➝9月1日頃
二百二十日(にひゃくはつか)
二百十日と同じく台風襲来の注意喚起
立春を第1日目として220日目
➝9月11日頃
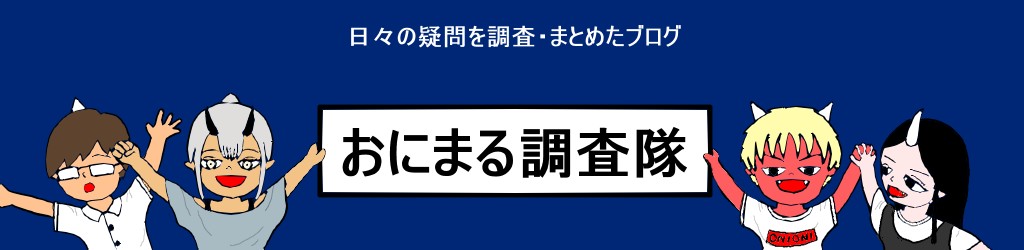
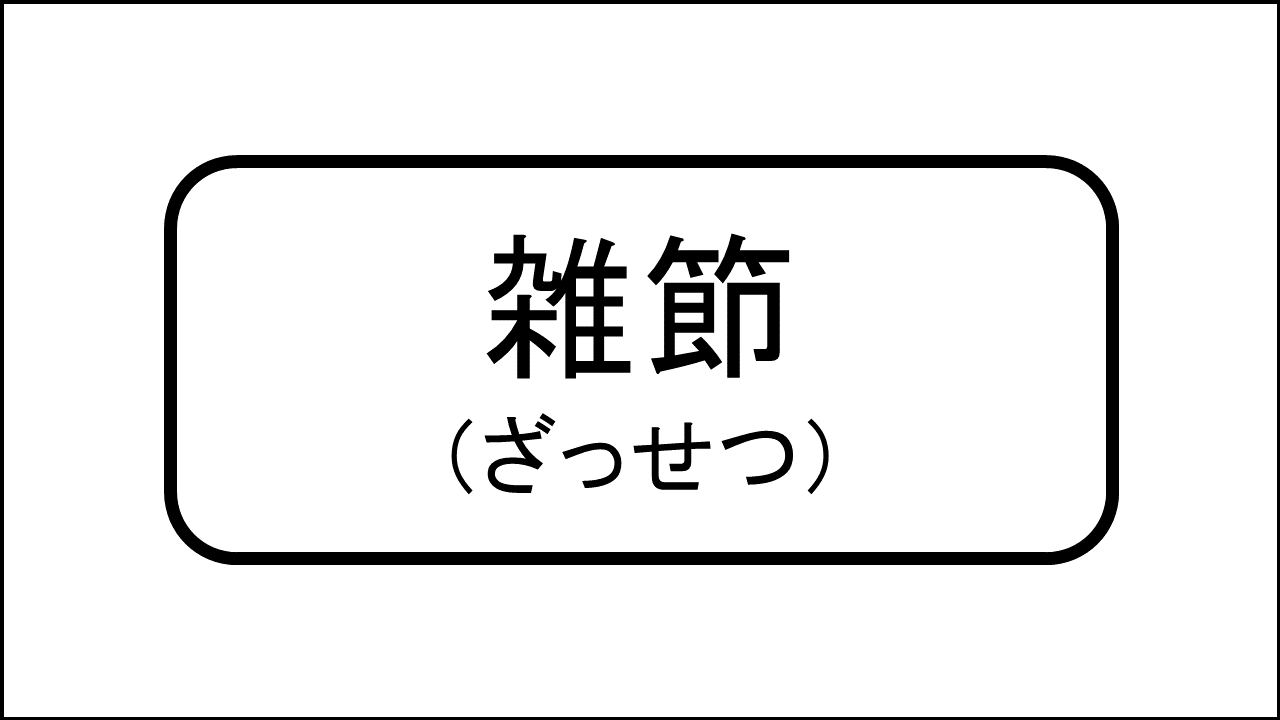
コメント