
長寿祝い
長寿祝いは、60歳以降の
10歳ごとの節目やゾロ目の歳に行われる
長寿祝い一覧
| 年齢 | 祝名 | 読み |
|---|---|---|
| 満60歳 | 還暦 | かんれき |
| 70歳 | 古希 | こき |
| 77歳 | 喜寿 | きじゅ |
| 80歳 | 傘寿 | さんじゅ |
| 88歳 | 米寿 | べいじゅ |
| 90歳 | 卒寿 | そつじゅ |
| 99歳 | 白寿 | はくじゅ |
| 100歳 | 百寿 | ひゃくじゅ ももじゅ |
| 108歳 | 茶寿 | ちゃじゅ |
| 111歳 | 皇寿 | こうじゅ |
| 満120歳 | 大還暦 | だいかんれき |
長寿祝いは数え年
長寿のお祝いは、
数え年が主流の時代から行われてきたもの
そのため本来は数え年にて祝うのが一般的だが、
現在では満年齢にて祝う傾向もある
還暦は満年齢の「60歳」
(数え年では「61歳」)
還暦に関しては干支が一回りし、
生まれた年と同じ干支の年に祝うという性質上、
満年齢60歳の時にそのタイミングとなる
長寿祝いの由来
還暦(かんれき)
『 満年齢60歳 』
(数え年では「61歳」)
干支が60年で一巡し、
再び生まれた年の干支に還るという節目を祝う
古希・古稀(こき)
『 70歳 』
中国の唐時代の詩の一節
「人生七十古来稀也」に由来する
詩の意味は、
「70年生きる人は古くから稀なり」、
当時、70歳まで生きる人は稀であった
喜寿(きじゅ)
『 77歳 』
「喜」の漢字の草書体が、
「七十七」に見えることに由来
傘寿(さんじゅ)
『 80歳 』
「傘」の略字が、
「八十」に見えることに由来
米寿(べいじゅ)
『 88歳 』
「米」の字を分解すると、
「八・十・八」から出来ていることに由来
卒寿(そつじゅ)
『 90歳 』
「卒」の略字「卆」が、
「九十」と読めることに由来
白寿(はくじゅ)
『 99歳 』
「百」の字から「一」を取ると、
「白」になることから
(100-1=99)
百寿(ひゃくじゅ・ももじゅ)
『 100歳 』
「百歳」であることから
「紀寿(きじゅ) 」と呼ばれることもある
(100年が1世紀にあたることから)
茶寿(ちゃじゅ)
『 108歳 』
「茶」の字を分解すると
「十・十・八十八」となることから
(10+10+88=108)
皇寿(こうじゅ)
『 111歳 』
「皇」の字を分解すると「白」と「王」
「白」は99を表す(「白寿」を参照)
「王」をさらに分解すると「一・十・一」
これらをすべて足すと、
「99+1+10+1=111」となることに由来
大還暦(だいかんれき)
『 満年齢120歳 』
(数え年では「121歳」)
2回目の還暦を祝うもの
120年で干支が2巡し、
再び生まれた年の干支に還るという節目を祝う
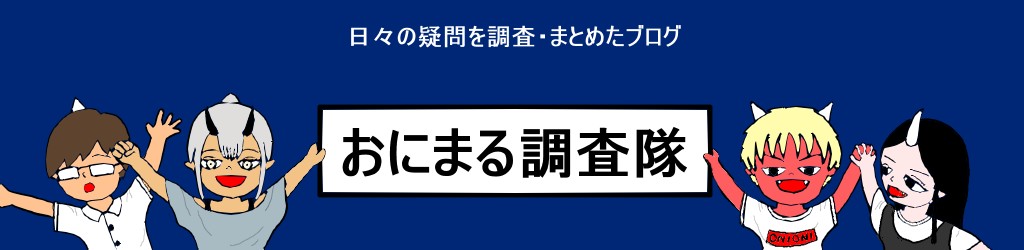
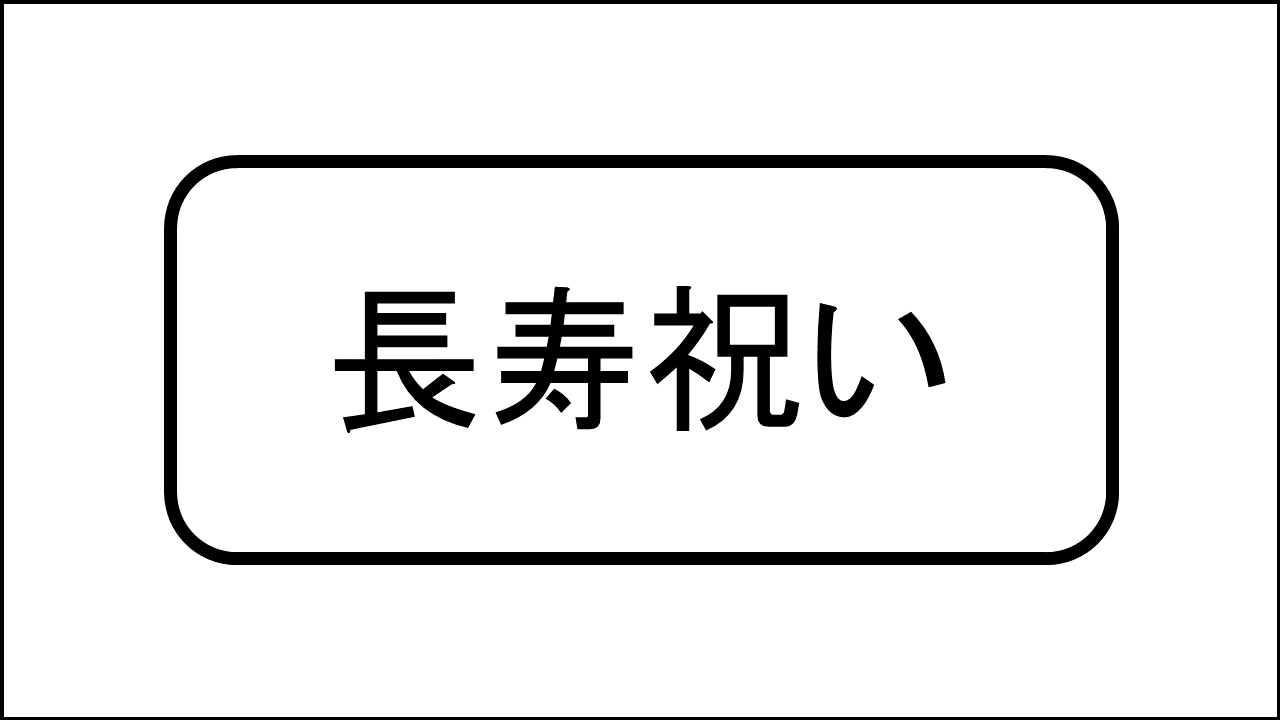
コメント