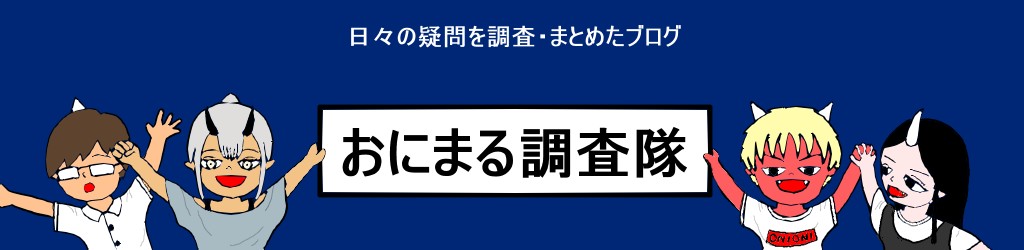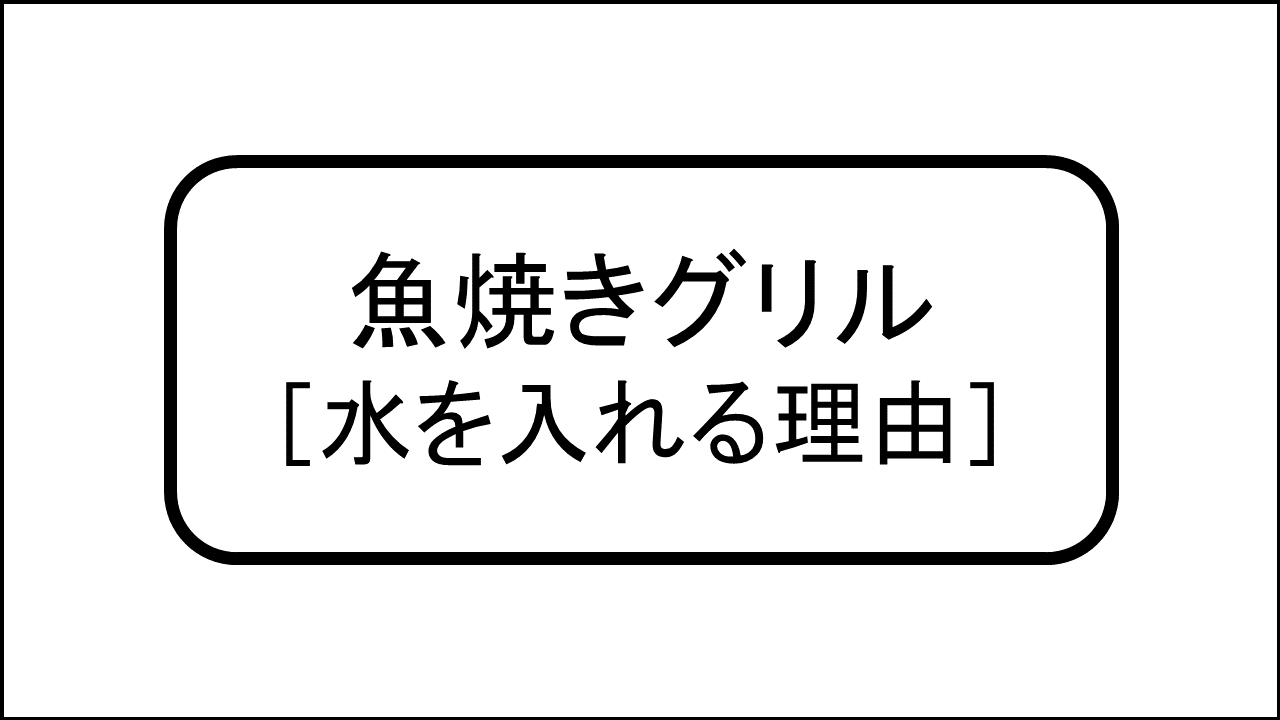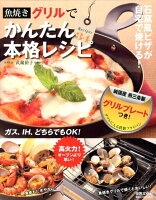魚焼きグリル
直火などの熱源による「放射熱」と
グリル庫内の気流による「対流熱」によって
食材を焼き上げる調理器具
基本的にガスコンロの一部として存在する
庫内温度
グリル庫内は300℃~400℃の高温になり、
トースターやオーブンのように
利用することもできる万能調理器具
(トースター:200℃~250℃程度)
(オーブン :最高温度300℃程度)
グリルの受け皿に水を入れる理由
グリルの受け皿に水を入れる理由は以下など
• 発煙の防止
• 受け皿の焦げ付き防止
• 食材の焦げ付き防止
発火の防止
脂が、高温になった受け皿に落ちると、
脂が発火温度になり発火の原因となる
受け皿に水があることで、受け皿の温度上昇を防ぎ、
落ちた脂も冷やすことができ、発火を防止
発煙の防止
脂が、高温になった受け皿に落ちると、
煙が発生する原因となってしまう
受け皿に水があることで、受け皿の温度上昇を防ぎ、
落ちた脂も冷え、水中に吸収され、発煙を防止
(煙を抑えることで、匂いの充満も軽減される)
受け皿の焦げ付き防止
受け皿に水があることで、
落ちた脂や汁による受け皿の焦げ付きを防止
食材の焦げ付き防止
受け皿に水があることで、グリル内の温度上昇を防ぎ、
また、蒸し焼きのような効果も得られることで、
食材の焦げ付きを抑える
魚焼きグリルの種類
ガスコンロの魚焼きグリルには
「水ありタイプ」と「水なしタイプ」がある
水ありグリル(片面焼き)
最も一般的な魚焼きグリル
グリルの受け皿に水を入れて使用し、
バーナーが上火のみで片面ずつ魚を焼くタイプ
メリット
一般的なものであり、価格が安め
デメリット
• 水を入れるため、準備・手入れの手間が多い
• 両面焼きに比べ、焼き上げるのに時間がかかる
• 食材を途中でひっくり返す必要がある
(手間がかかるうえ、身が崩れやすい)
水なしグリル(片面焼き・両面焼き)
バーナーやヒーターの位置が工夫されていたり、
受け皿周辺に冷えた空気を流す構造などにより、
受け皿が高温にならないようになっているグリル
受け皿が高温にならないので、
「フッ素」や「クリアコート」のコーティングが可能で、
それらを施して手入れ性を格段に向上させたものもある
水蒸気が出ず、蒸したような状態にならないので、
表面がパリッと焼き上がる
水なしグリル(片面焼き)
グリルの受け皿に水を入れずに使用し、
バーナーが上火のみで片面ずつ魚を焼くタイプ
メリット
水を入れる手間がいらない
デメリット
• 食材を途中でひっくり返す必要がある
• 両面焼きに比べ、焼き上げるのに時間がかかる
• 食材を途中でひっくり返す必要がある
(手間がかかるうえ、身が崩れやすい)
水なしグリル(両面焼き)
グリルの受け皿に水を入れずに使用し、
上下のバーナーで魚を両面同時に焼くタイプ
メリット
• 水を入れる手間がいらない
• 一度に両面焼けるので、片面焼より早く焼ける
• 途中でひっくり返す必要がない
デメリット
一般的なものに比べて価格が高い
魚焼きグリルの手間を軽減
魚焼きグリルは使用後の洗浄に手間がかかるが、
以下などを利用して、手間を軽減することができる
• 片栗粉の利用 ……(受け皿)
• 重曹の利用 ………(受け皿)
• グリルストーンの利用…(受け皿)
• 受け皿シートの利用 …(受け皿)
• グリルプレートの利用…(網・受け皿)
アルミホイルの利用(網)
網は洗いにくく、汚れがこびりついたり、
焦げ付いてしまうと洗うのが大変
そこで、食材を直接網に乗せるのではなく、
網の上にアルミホイルを敷いてから焼くようにして、
使用後に捨てるようにすれば、後片付けが楽になる
また、このアルミホイルを用いた方法は
ししゃもなどの細い魚や小魚などを調理する際に、
網の隙間から落下することも防ぐこともできる
注意事項
そのまま使用すると、
アルミホイルの上で脂が溜まり、高温になるので、
数か所穴を空けて脂を受け皿に落とすようにする
アルミは金属のため、グリル内の温度では燃えないが、
耐熱温度を超えると溶けて穴が開いてくることはある
(耐熱温度に注意し、耐熱温度が高いものを使う)
また、直火や熱源に触れていると、
燃える危険性はあるので、使用の際は注意する
片栗粉の利用(受け皿)
受け皿に入れる水に片栗粉を溶かして入れておくと
使い終わったあと洗浄がしやすい
使用後、脂と一緒に固まるので、
それを取り外して捨てれば、ほぼ汚れが残らない
方法
片栗粉の分量は、大さじ4杯程度
(水200mL程度の場合)
①. 片栗粉と水を混ぜ合わせ、受け皿に入れる
②. 魚などの食材を焼く
(片栗粉水はトロトロの状態となり、脂を吸収する)
③. 使用後しばらく放置する
(片栗粉水が冷えて固まっていく)
④. 冷えて固まった片栗粉水を取り外し、捨てる
⑤. 受け皿を軽く洗い流して洗浄終了
重曹の利用(受け皿)
重曹は油汚れや臭いを分解する力があり、
以下の3通りのような使い方ができる
①. 重曹を敷く
受け皿に水のかわりに重曹を敷いておくと、
落ちてきた脂を重曹が吸収して受け皿が汚れずにすむ
(そのままゴミ箱に捨てればよいので手入れが楽)
②. 重曹を洗浄剤として使う
使用後、特にまだ水が温かいうちに重曹を入れておけば、
洗浄効果が高くなって汚れが落ちやすくなる
(重曹は汚れと馴染んで落ちやすくさせる効果がある)
③. 水と混ぜて受け皿に入れておく
①と②を足したような効果が得られる
グリルストーンの利用(受け皿)
水の代わりに小さな石(グリルストーン)
を敷き詰めることにより、石が脂や臭いを吸収
遠赤外線効果も発生し、
炭火焼きのように焼き上がるともされる
受皿シートの利用(受け皿)
水の代わりに受け皿シートを入れる
(保水性が高く燃えにくい材質のシート)
脂や気になる臭いも吸い取り、
使用後はシートを捨てるだけなので、片づけが簡単
グリルプレートの利用(網・受け皿)
網の上に載せて使うプレート
基本的に鉄板部が波型になっており、
焦げ付きを防ぐコーティングもされている
BBQなどでも網の上に置いて活用できる