
カラーテレビ(ディスプレイ)の仕組み
カラーテレビ(ディスプレイ)の画面は、
基本的に「赤(R)」「緑(G)」「青(B)」の
光の三原色と言われる3色で構成されている
(例外として4色を使ったものなどもある)
光の三原色の1セット
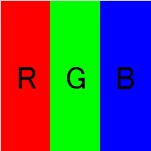
隣り合わせの3色(各三原色)の媒体に
それぞれ任意の明るさの光を当てる
(もしくは媒体自体を任意の明るさに光らせる)
隣接した光は遠目から見ると、
混ぜ合わさった状態で見えるようになる
この視覚効果を利用することで、
再現したい色を作り出す
「赤(R)」「緑(G)」「青(B)」の3色は
光の三原色といわれ、この3色の
明るさの組み合わせで様々な色が表現できる
三原色セットを複数並べたもの
(=ディスプレイ)
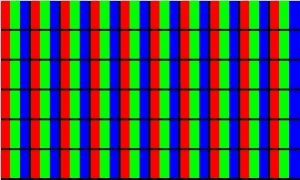
三原色の3色を1組とした粒(ドット)を
何十万、何百万…と配置することにより、
画像が再現される
その画像の積み重ねが映像、動画になる
(パラパラ漫画のようなイメージ)
光の三原色による色の組み合わせ
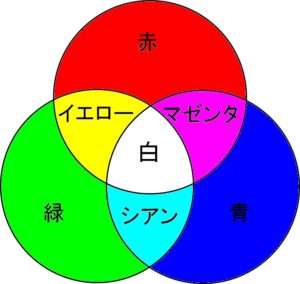
主な組み合わせとしては、
3色それぞれを256種類の明るさの違いで分類し、
それを組み合わせるというものがある
「0(暗)⇔ 255(明)の256種類」
その組み合わせによって再現できる色の数は、
16,777,216色
「256×256×256=16,777,216(色)」
2進数(「0」と「1」のみを用いた表現)において
8桁(8ビット)で表現できる組み合わせが256種類
「00000000」= 0 「00000001」= 1 「00000010」= 2 「00000011」= 3 ・ ・ ・ ・ 「11111110」= 254 「11111111」= 255
3色全て最大の明るさで組み合わせれば「白」
• 赤(255)+緑(255)+青(255) ⇒「白」
3色全てに光を当てなければ「黒」
• 赤(0)+緑(0)+青(0) ⇒「黒」
その他、
• 赤(255)+緑(255)+青(0)⇒「イエロー」
• 赤(0)+緑(255)+青(255)⇒「シアン」
• 赤(255)+緑(0)+青(255)⇒「マゼンタ」
など
画素数
その画像を構成している画素(ピクセル)が
どれだけ用いられているかを表す数値
多いほど細かく色を表現することができ、
より鮮明な画像となる
少なければより粗い画像となる
光の三原色1セットを
「1画素」「1ピクセル」などとし、
その数により画像の鮮明さを表したりする
TVディスプレイなどにおいて、
HDや4Kといった表現が用いられるが、
それらの画素数は以下などの通り
ちなみにデジタルテレビ放送の標準比率は
「16:9」であり、以下の長辺×短辺ピクセルは、
その比率に準じた数値
4K
「3840×2160ピクセル(829万4400画素)」
4Kは「4000」という意味で、
長辺方向の画素が約4000あることに由来
短辺方向の画素数から「2160p」と
表現されることもある
フルHD(フルハイビジョン)
「1920×1080ピクセル(207万3600画素)」
“フル”が付くのは、
通常のデジタルテレビ放送において
規格上の最大解像度であることに由来
短辺方向の画素数から「1080p」と
表現されることもある
HD(ハイビジョン)
「1280×720ピクセル(92万1600画素)」
デジタルテレビ放送において
もともと主流である画素数
短辺方向の画素数から「720p」と
表現されることもある
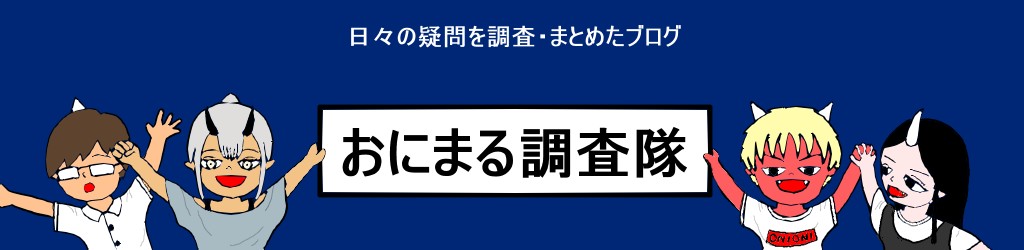
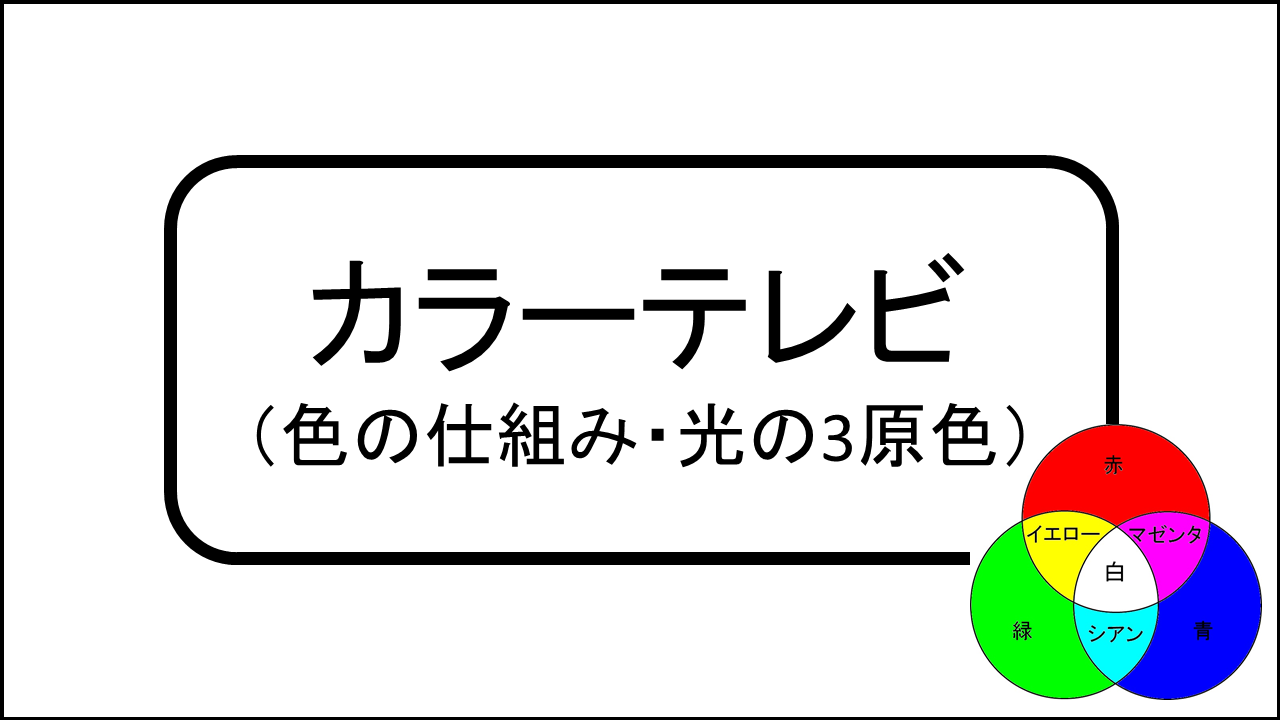
コメント