
十二支
十二支(じゅうにし)とは、
「子」「丑」「寅」「卯」「辰」「巳」
「午」「羊」「申」「酉」「戌」「亥」
の12種のこと
これを用いて方角、月日、時間などを表していた
十二支のことを「えと」と呼んだりするが、
「えと」とは本来、十干(じっかん)と十二支の組み合わせ
「十干十二支」を表す「干支(かんし、えと) 」のこと
十二支の動物と読み
| 十二支 | 漢字の読み | 動物 |
|---|---|---|
| 子 | し | 鼠:ねずみ(ね) |
| 丑 | ちゅう | 牛:うし |
| 寅 | いん | 虎:とら |
| 卯 | ぼう | 兎:うさぎ(う) |
| 辰 | しん | 龍:りゅう(たつ) |
| 巳 | し | 蛇:へび(み) |
| 午 | ご | 馬:うま |
| 未 | び | 羊:ひつじ |
| 申 | しん | 猿:さる |
| 酉 | ゆう | 鳥:とり |
| 戌 | じゅつ | 犬:いぬ |
| 亥 | がい | 猪:いのしし(い) |
十二支の漢字と動物の漢字が異なっているのは、
もともと十二支として使われていた漢字に、
それぞれ動物を割り当てたためとされる
そのため、十二支で用いられている漢字と
それぞれの動物には本来、関連はない
動物が割り当てられた理由
当時、全員が読み書きができたわけではないため、
動物を割り当てることでわかりやすくし、
十二支を広く浸透させるためであると推測される
十二支で表す時刻・方角
| 十二支 | 時刻 | 方角 |
|---|---|---|
| 子(ね) | 23~1時 | 北 |
| 丑(うし) | 1~3時 | 北東(北より) |
| 寅(とら) | 3~5時 | 北東(東より) |
| 卯(う) | 5~7時 | 東 |
| 辰(たつ) | 7~9時 | 南東(東より) |
| 巳(み) | 9~11時 | 南東(南より) |
| 午(うま) | 11~13時 | 南 |
| 未(ひつじ) | 13~15時 | 南西(南より) |
| 申(さる) | 15~17時 | 南西(西より) |
| 酉(とり) | 17~19時 | 西 |
| 戌(いぬ) | 19~21時 | 北西(西より) |
| 亥(い) | 21~23時 | 北西(北より) |
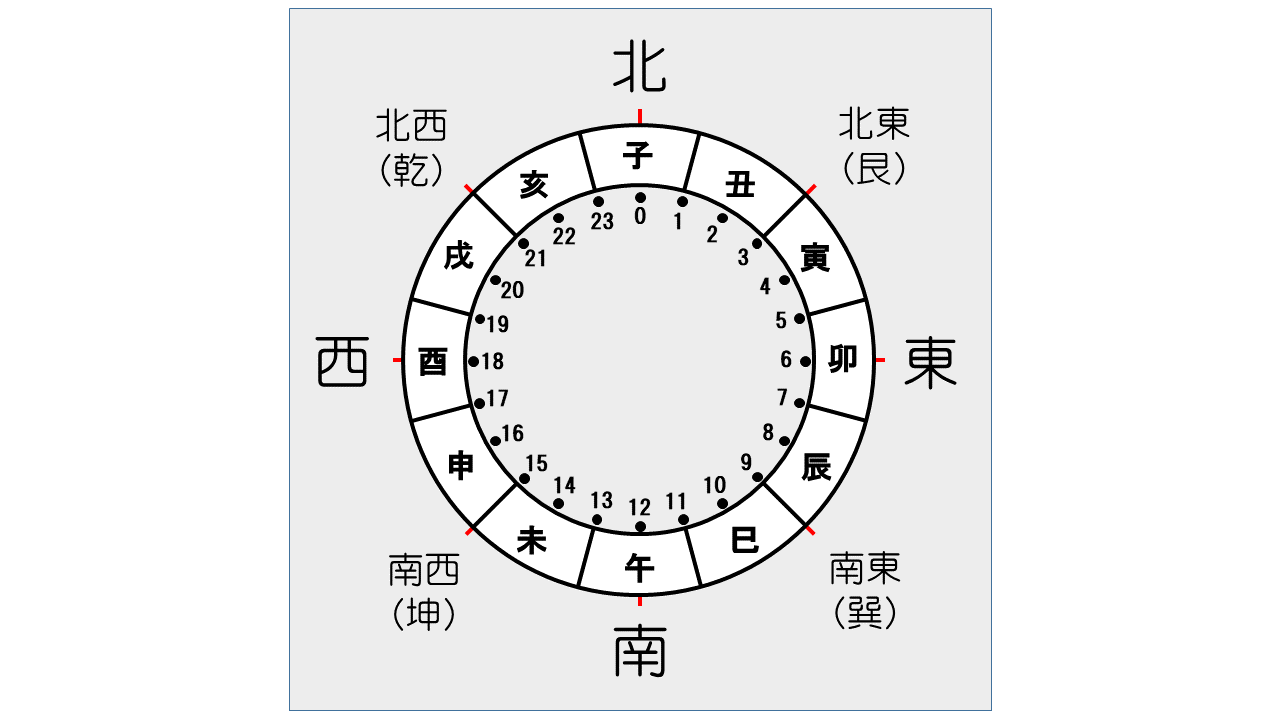
十二支を用いた時間用語
12時ちょうど➝「正午」
12時以前➝「午前」
12時以後➝「午後」
十二支を用いた方角用語
北東➝「うしとら(艮) 」
(「牛(うし) 」と「寅(とら) 」の間)
南東➝「たつみ(巽) 」
(「辰(たつ) 」と「巳(み) 」の間)
南西➝「ひつじさる(坤) 」
(「未(ひつじ) 」と「申(さる) 」の間)
北西➝「いぬい(乾) 」
(「戌(いぬ) 」と「亥(い) 」の間)
十二支の歴史
古代中国において用いられていたものが
日本に伝来したとされる
中国においては殷時代には
すでに使用していたとされる
(殷時代=日本では縄文時代頃)
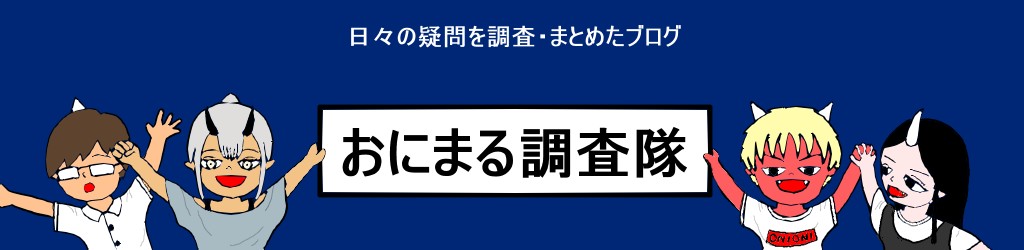
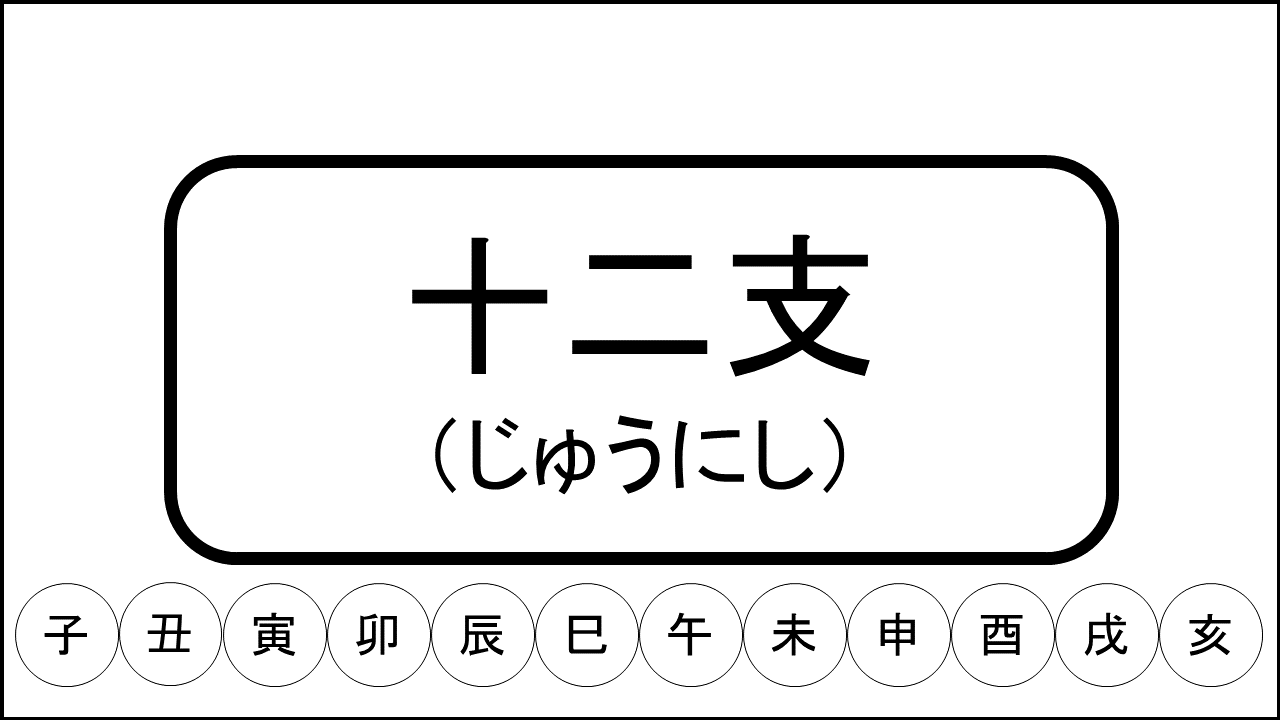
コメント