
「こうよう」と「もみじ」の違い
「紅葉」という漢字を用いて
「こうよう」「もみじ」と2つの読み方があるが、
それぞれ読み方によって意味するものは異なる
【紅葉(こうよう)】
現象や景色をいう時に用いられる
主に落葉樹の葉が秋付近の季節に
葉が落ちる前に赤や黄色に変化する
自然現象もしくは色鮮やかな景色のこと
色の区別に関係無く呼ばれる場合と、
赤い場合のみを指す場合がある
【紅葉(もみじ)】
植物自体をいう時に用いられる
一般的に「紅葉している楓(かえで)」のこと
もしくは、ひときわ赤色に目立つ葉のこと
植物自体を「紅葉(こうよう)」と呼んだり、
景観に対して「紅葉(もみじ)している」
とは言わない
「かえで」と「もみじ」の違い
どちらも分類上はカエデ科カエデ属の植物
一般的な区別
【かえで(楓)】
カエデ科カエデ属の植物の総称
落葉樹のものが多いが常緑樹もある
英語圏では一般に「Maple(メープル)」
【もみじ(紅葉)】
「楓」のうち、秋に葉が色づいたものや
ひときわ赤く色づいたものの総称
葉の切れ込みが深く、
小ぶりで鮮やかな赤色
「イロハモミジ」「ヤマモミジ」など、
もみじと名の付く楓もある
葉の特徴による区別
【かえで】
• 葉の切れ込みが浅いもの
• 切れ込みが3つ程度のものなど
【もみじ】
• 葉の切れ込みが深いもの
• 切れ込みが5つ以上で手のひら状のもの
「かえで」「もみじ」の語源
【かえで】
蛙(かえる)の手の様に見えることから、
「蛙手(かえるで)」⇒「かえで」
と転じたとされる説が一般的に知られる
【もみじ】
染め物の「揉み出づ(もみいづ)」に由来する
という説が一般的に知られる
紅花染めに使う紅花(べにばな)の花びらには
紅と黄の2種類の色素が含まれており、
これを水や灰汁に浸けて揉むことで抽出
(黄色や紅色の染料を「揉み出す」)
色の抽出の際の様子と楓の紅葉する様を重ね、
「揉み出づ」や「もみずる」と表現し、
そこから転じて「もみじ」となったとされる
葉の色が変化するしくみ
葉の中には、
「クロロフィル(緑の色素)」と、
「カロテノイド(黄の色素)」がある
クロロフィルが葉の老化反応によって分解し、
カロテノイドは分解されず残ることで、
葉が緑色から黄色に変化
「アントシアニン(赤の色素)」の生成による
同種の植物でも色の違いが出るのは、
植物それぞれの色素を作り出す能力の違いや、
自然条件の違いが複雑に絡み合う結果による
葉緑素ともいわれる緑色の色素
光合成によって光エネルギーを吸収する役割を持つ
動植物界に広く存在する
黄、橙、赤、紫などの色素の総称
(「楓」においては黄の色素)
光の害から植物を守るために機能する
クロロフィルが分解することにより、
カロテノイドが目立つようになる
植物界に広く存在する
赤、青、紫などの色素の総称
(「楓」においては赤の色素)
光の害から植物を守る
働きをすると考えられる
クロロフィルやカロテノイドが
分解される際に生成される
「楓(落葉樹)」の1年
葉緑体(クロロフィルなど)が光を吸収して
活発に光合成を行い、木に栄養を蓄える
日照時間が短くなって光合成が減り、
栄養を幹に回すために葉の栄養がなくなっていく
(それにより「クロロフィル」が分解)
➝葉が「赤色」や「黄色」に変化する
栄養供給を断絶された葉は老化し、落葉する
これによって、水分やエネルギーが
葉のために消費されるのを防ぐことができる
紅葉狩り(もみじがり)
「狩り」の元々の意味は、
野山で獣や鳥を追い立てて捕らえること
そのうち植物に対しても用いるようになった
(「いちご狩り」「キノコ狩り」など)
さらに山野などに分け入っていく行為自体や、
そこで楽しむ景観などにも用いられるようになり、
「紅葉狩り」という言葉が生まれたとされる
実際に狩る、採るのではなく
「観賞」を楽しむ
黄葉(こうよう・おうよう)
赤く色づく葉を「紅葉(こうよう)」というが、
黄色い葉になることは「黄葉(こうよう・おうよう)」
黄でも赤でも、葉が色づくことや色づいた
景色全体を「紅葉」とされることが多いため、
「黄葉」という言葉は、あまり使われない
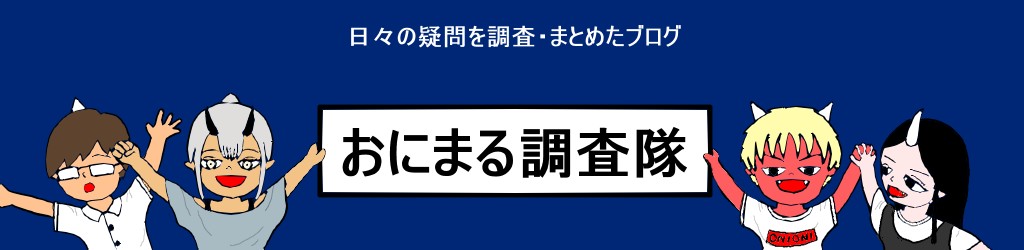
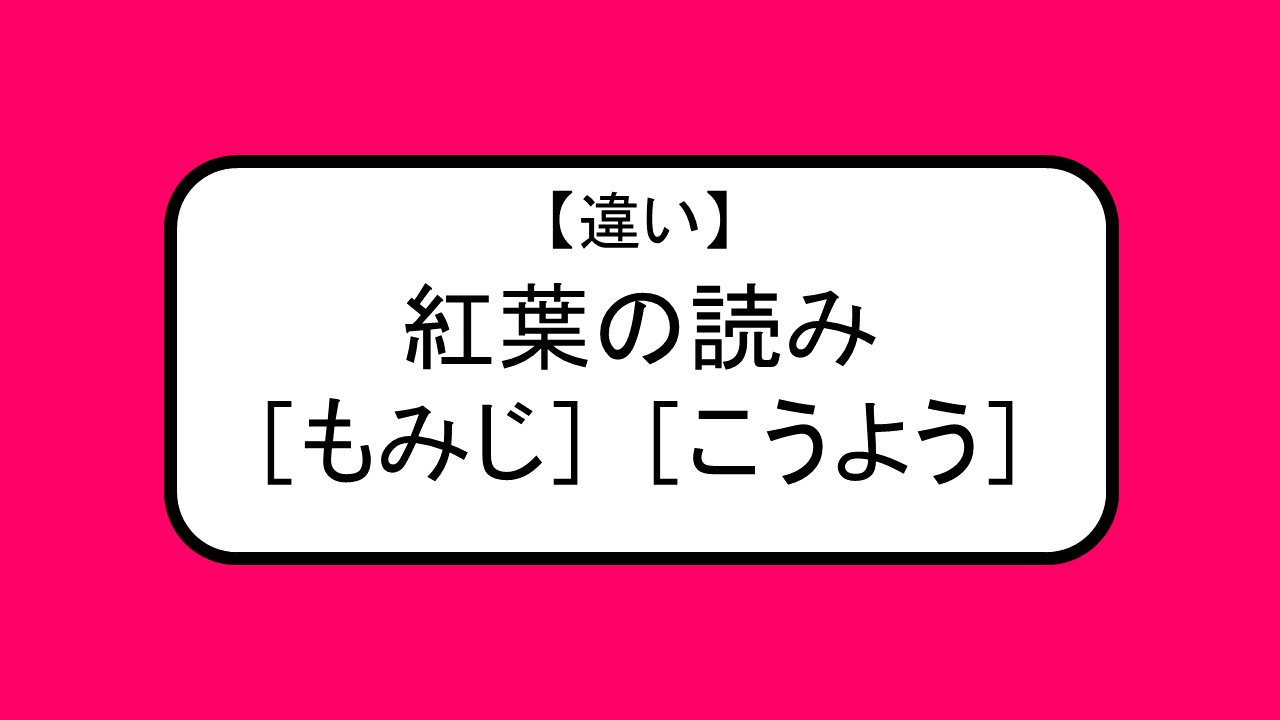
コメント