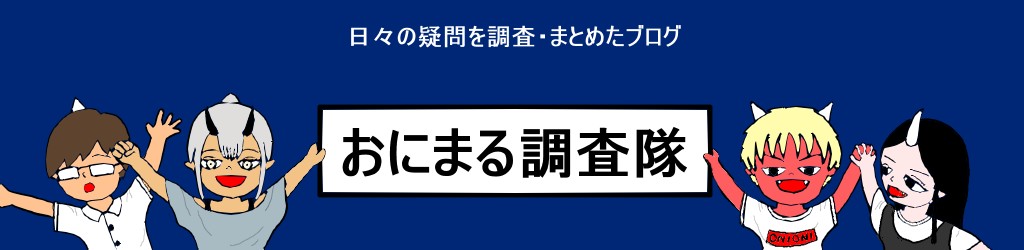川と海の境界
一般的に「川」と「海」の境は、
河口部の両岸を結ぶ線であるとされている
ただし厳密には、
適用する法律によって様々、所管する官庁も異なり、
個々に境界線が取り決められている
「河口」…川から海に注いでいくところ
「淡水」から「海水」へ
川と海の境界では、
いきなり「淡水」が「海水」になるわけではない
境界付近では「淡水」と「海水」が混在している
この混在した状態の水は「汽水」と呼ばれる
(汽水が占める区域 =「汽水域」)
一般的には河口付近が汽水域にあたるが、
海に近い湖では、湖そのものが汽水域だったりする
(そういった湖は「汽水湖」とも呼ばれる)
汽水域での「淡水」「海水」
境界は潮の干満(満ち引き)によって変動する
【満潮時】海水は河口をさかのぼる
【干潮時】淡水がより下流まで流れ込む
汽水域では一般的に、
淡水と海水が「二層構造」となる
おおまかにいうと、
河川の上流から流れ込んだ淡水が「上層」に、
塩分濃度が高く比重の重い海水が「下層」に存在
汽水の塩分濃度
一般的に、
・淡水の塩分濃度➝「0.05%未満」など
・海水の塩分濃度➝「3.5%前後」など
汽水の塩分濃度
淡水と海水の間の「0.05%~3.5%」など
汽水域の魚
汽水域には、淡水魚、海水魚を問わず、
たくさんの種類の魚が入り込んでくる
淡水魚と海水魚の違い
淡水魚と海水魚の体液濃度はほぼ同じであり、
大きな違いはその調整機能にある
淡水魚
体液よりも薄い淡水が体内に入り過ぎると
体液濃度が薄まってしまう
体内に入り込んだ淡水の塩分と水分のうち
「水分」を尿等でより多く排出することで
体液濃度を調整
海水魚
体液よりも濃い海水が体内に入り過ぎると
体液濃度が濃くなってしまう
体内に入り込んだ海水の塩分と水分のうち
「塩分」をエラ等でより多く排出することで
体液濃度を調整
これらの機能を用いることで、
各々の生息地において生活が可能となっている
環境が一気に変わると、
変化に機能が対応できず、生きていけない
汽水域に入り込んだ場合
淡水魚も海水魚もそれぞれ、
ある程度の塩分変化には対応可能
このため汽水域には、
淡水魚、海水魚どちらも存在したりする